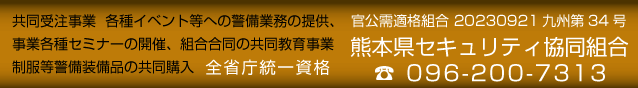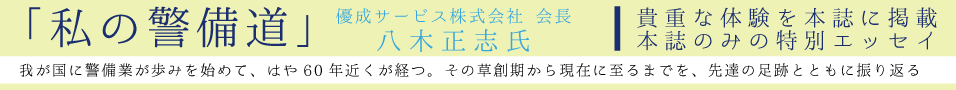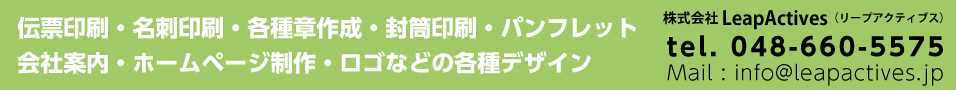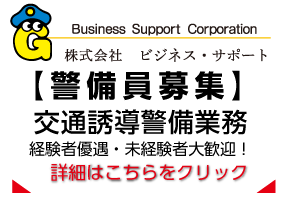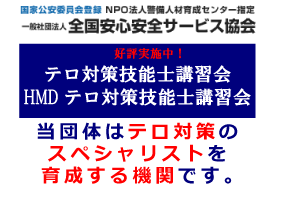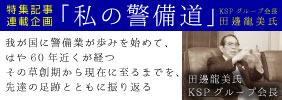令和4年における警備員減少に切迫した危機感 “全国警備業協会「特定技能」制度で人材確保”

全国警備業協会(中山泰男会長)は、特定技能制度による外国人の人材確保に関しては、2020年外国人雇用を検討する作業部会(折田康徳部会長:(株)にしけい)によって検討されてきた。
警備業界の外国人の人材活用については、検討部会おいて警備業協会加盟員の意向調査、特定技能制度を活用しやすい種別、雇用後のサポート体制などを検討し、2021年にアクションプランをまとめた。
全国警備業協会(以下「全警協」という。)では、9月26日に開催された理事会をへて関係省庁に特定技能制度を導入し、外国人労働者を受け入れることの要望を「予算・税制等に関する要望書」に盛り込んだ。
全警協は、特定技能制度で活用する警備業務は、雇用後のサポートのし易さと、最も人材不足が深刻な空港保安警備業務から進め、次いで施設警備業務、交通誘導警備業務へ広げて行く構想である。また、並行して日本語学校などの語学留学生をアルバイトで雇用しつつ、卒業後は特定技能制度に移行して、雇用するなどの方法も検討していくことも構想にある。
特定技能制度の今後は、国の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の答申を受けて制度の見直しが図られることから、全国警備業協会はその動向を注視していくこととなる(出典;警備保障タイムス)。
いずれにしても、令和4年の警備業の概況によって明らかになった6年ぶりの警備員の減少は、警備業界に切迫した危機感をもたらした。
令和4年の警備員数の減少、警備業界に危機感“一過性の減少ではない?”
警備員数は令和3年まで増えてきた。中でも令和元年は1万6,000人、令和2年には1万7,000人と増加し、コロナ過の令和3年でも1,500人増えた。しかし、新型コロナの感染予防の影響を受けて、一部の年齢層では、この年から警備員数に減少の兆しが出始めていた。
《警備員の年齢別・男女別》
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 増 減 | |
| 570,727 | 588,364 | 589,938 | ▼582,114 | ▼7,824 | |
| 30歳未満 (構成比) |
57,043 (10.0) |
61,847 (10.5) |
61,918 (10.5) |
▼59,122 (10.2) |
▼2,796 (▼0.3) |
| 男性 | 46,660 | 50,130 | 50,496 | ▼48,554 | ▼1,942 |
| 女性 | 10,383 | 11,717 | 11,432 | ▼10,568 | ▼864 |
| 30~39歳 (構成比) |
59,545 (10.1) |
▼59,202 (10.1) |
▼58,719 (10.0) |
▼55,824 (9.6) |
▼2,895 (0.4) |
| 男性 | 54,614 | ▼53,913 | ▼53,487 | ▼50,674 | ▼2,813 |
| 女性 | 4,931 | 5,289 | ▼5,232 | ▼5,150 | ▼82 |
| 40~49歳 (構成比) |
90,566 (15.9) |
91,523 (15.6) |
▼89,448 (15.2) |
▼85,397 (14.7) |
▼4,051 (0.5) |
| 男性 | 83,723 | 84,406 | ▼82,473 | ▼78,593 | ▼3,880 |
| 女性 | 6,843 | 7,117 | ▼6,975 | ▼6,804 | ▼171 |
| 50~59歳 (構成比) |
108,533 (19.0) |
111,503 (19.0) |
113,631 (19.3) |
▼113,511 (19.5) |
▼120 (0.2) |
| 男性 | 101,404 | 103,854 | 105,759 | ▼105,434 | ▼325 |
| 女性 | 7,129 | 7,649 | 7,872 | 8,077 | 205 |
| 60~64歳 (構成比) |
78,295 (13.7) |
▼77,383 (13.2) |
▼77,010 (13.1) |
▼75,593 (13.0) |
▼1,417 (0.1) |
| 男性 | 75,096 | ▼74,192 | ▼73,641 | ▼72,016 | ▼1,625 |
| 女性 | 3,199 | ▼3,191 | 3,369 | 3,557 | 188 |
| 65~69歳 (構成比) |
89,464 (15.7) |
▼86,950 (14.8) |
▼83,392 (14.1) |
▼80,760 (13.9) |
▼2,632 (0.2) |
| 男性 | 86,902 | ▼84,584 | ▼80,849 | ▼78,147 | ▼2,702 |
| 女性 | 2,562 | ▼2,366 | 2,543 | 2,613 | 70 |
| 70歳以上 (構成比) |
87,281 (15.3) |
99,956 (17.0) |
105,820 (17.9) |
111,907 (19.2) |
6,087 (1.3) |
| 男性 | 85,355 | 97,956 | 103,421 | 109,325 | 5,904 |
| 女性 | 1,926 | 2,203 | 2,399 | 2,582 | 183 |
令和4年には、69歳以下の全ての年齢層で減少しており、中でも49歳以下の警備現場の精鋭層が減少しているのが極めて残念である。
また、令和4年の減少した警備員の雇用形態を見ると、常用警備員は3,915人、臨時警備員は3,909人とほぼ半々となっており、継続的な警備現場でもコロナによる警備員の削減が余儀なくされ、常用警備員の雇用が減少した可能性が数字からも窺える。
さらに、警備員の年齢構成からみると、49歳以下の構成比率は減少しており、60歳以上の構成比率は46.1パーセントと増加していることから、警備業界もビルメンテナンス業界と同様に高齢化が年々進んでいることに間違いはない。
日本の人口減少傾向を見るに当たり、令和4年の警備員数が減少したのが一過性の減少ではなく、今後とも減少するものと断定した上で、人材確保政策を業界全体で取り組む必要がある。
その点では、全警協の打ち出した特定技能制度を活用して、外国人による雇用の確保政策は間違いない。
ただ、特定技能制ついては、外国人を安く使用できるなど安易な運用を行うことがないよう、活用する警備業者が正しい制度運用を理解して進めていかなければ、特定技能難民が生じるなど人材の供給国から非難を受けることになる。このようなことが生じないためには、管理団体(協同組合)と全警協や都道府県警備業協会の連携とともに、協会の指導体制と外国人へのサポート体制の確立が極めて重要となる。
ただ、特定技能で活用する能力試験と日本語試験の確立は容易にできると思われる。なぜかといえば、警備業界には国家資格である技能検定制度があるから、特定技能制度に必要な専門性の試験や日本語能力試験(N4)は、その警備種別の検定制度を活用すれば、専門的な能力試験も必要な日本語試験の内容や試験方法はそれほど難しくはないはずである。
特定技能制度の早期の実現に期待をしたい。