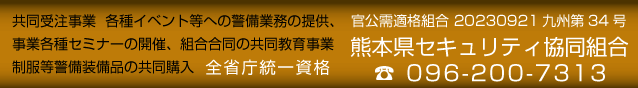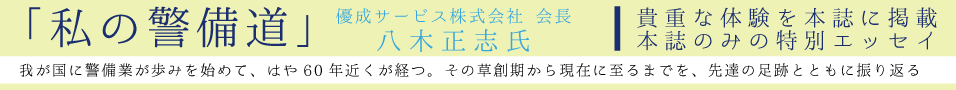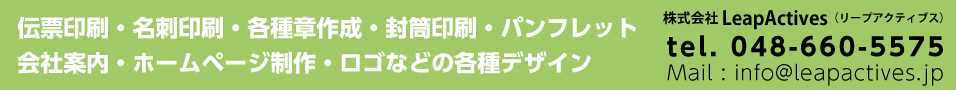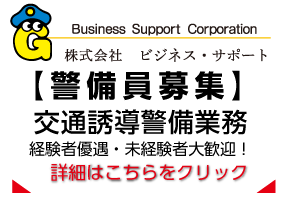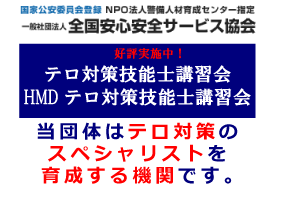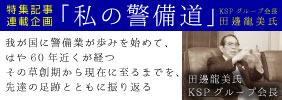【警備業関係用語】12月② 六何の原則(5W1H)・新任警備員教育・聴導犬・超音波センサー
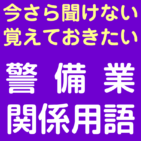
~今さら聞けない、覚えておきたい警備業関係用語~
各業界には業界特有の用語などがあり、警備業にもたくさんの用語があふれています。普段、何気なく使っている用語の意味を改めて確認してみませんか?
朝礼などでみなさんで確認するのもおすすめです。
1回につき4語の掲載で平日更新予定となります。
六何の原則(5W1H)(ろっかのげんそく)
警察機関等への連絡を簡潔、明瞭に行うための原則のこと(①何時(When)、②何処で
(Where)、③何人が(Who)、④何を(What)、⑤何故(Why)、⑥如何にして(How)
の6つを挙げている。)。
新任警備員教育(しんにんけいびいんきょういく)
新たに、警備業務に従事させようとする者に対して行う教育のこと。基本教育及び業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育があり、それぞれ当該対象者の検定等資格の有無、経験年数等によって教育時間数が異なる。
(警備業法第21条、同法施行規則第38条)
聴導犬(ちょうどうけん)
聴覚障害者を介助するよう訓練された犬のこと。玄関のブザー、湯の沸いたやかんの音、赤ちゃんの泣き声、自転車のベルや非常ベルの警報音など、生活に必要な様々な音の情報を知らせてくれる。
超音波センサー(ちょうおんぱせんさー)
超音波を利用して人の侵入を検知するセンサーのこと。